犬を飼っていると、愛犬の病気は常に気にかかりますよね。
ずっと元気だと思っていた愛犬も、気づいたときにはすでに病気を患っているかもしれません。
犬の病気の種類はさまざまですが、今回は「沈黙の臓器」とよばれ、症状が分かりにくい肝臓病にスポットをあてて解説します。
「定期的に検査しているからうちの子は大丈夫」といった油断は禁物です。
愛犬のちょっとした変化に気づくためにも、肝臓病の種類や症状を理解し、事前の予防を徹底しましょう。
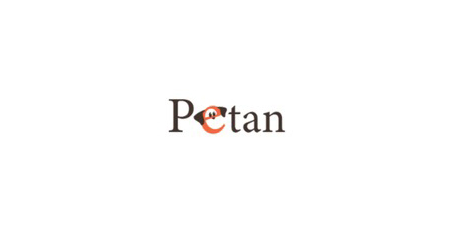 健康管理/病気
健康管理/病気犬の肝臓の役割
犬の肝臓は横隔膜の近くに位置し、体内で最も大きな臓器です。
外側左葉・内側左葉・方形葉・外側右葉・内側右葉・尾状葉の6つの葉に分けられています。
肝臓の役割としては、①栄養素の合成・貯蔵、②毒素の分解、③胆汁の分泌があげられるので、それぞれ詳しく解説します。
栄養素の合成・貯蔵
小腸で吸収された栄養素は血液によって運ばれ肝臓に流れ込みます。
その際、過剰に接種されたグルコースのような糖質をグリコーゲンというかたちに合成しなおし、いざというときのエネルギー源として貯蔵します。
蓄えられたグリコーゲンを再分解してグルコースに戻すことで、食事量が少ない場合でも血糖値を一定に維持できます。
毒素の分解
肝臓にはアンモニアのような毒素を分解する役割があります。
アンモニアはタンパク質の利用過程で発生する副産物ですが、そのまま放置すると神経系の症状を発生させる危険な物質です。
そのため、肝臓でアンモニアを尿素に分解し、尿として排泄できるように処理しています。
胆汁の分泌
胆汁とは、脂肪の消化・吸収に利用される消化液です。
古くなって壊された赤血球やコレステロール、コレステロールが分解される際に生成される胆汁酸などが主成分です。
胆汁は肝臓で常に作られており、消化に利用されるまでのあいだは胆嚢に一時保管されます。
その後、胃の中に食物が入ってくると必要に応じて十二指腸に送られ、脂肪の消化・吸収を促進する手助けをします。
犬の肝臓病の種類と症状
犬の肝臓病の種類と症状についてそれぞれ解説します。
急性肝炎
急性肝炎とは、肝臓部に急激な炎症が発生する病気です。
主に細菌やウイルス、寄生虫などが発症原因とされています。
急性肝炎によって肝臓がダメージを受けることで、次に解説する慢性肝炎に移行する可能性もあります。
急性肝炎の症状例は以下のとおりです。
- 食欲不振
- 多飲多尿
- 元気がない
- 腹部が膨れる
- 黄疸(目のまわりや歯茎が黄色くなる)
- 嘔吐
- 下痢
- 血便 など
症状が軽度であれば自然治癒も期待できる病気ですが、中度~重度になると嘔吐や血便、黄疸などの症状がみられます。
慢性肝炎
慢性肝炎とは、肝臓が慢性的に炎症を起こす病気です。
慢性的な肝臓の炎症が発生すると、肝臓が線維化し、肝硬変へ進行する恐れがあります。
慢性肝炎は、特発性と呼ばれる原因不明なものが多いです。
急性肝炎が進行すると慢性肝炎を発症する可能性が高くなるため、早期発見と治療が重要となります。
慢性肝炎の症状例は以下のとおりです。
- 食欲不振
- 多飲多尿
- 体重減少
- 元気がない
- 黄疸(目のまわりや歯茎が黄色くなる)
- 嘔吐
- 下痢
- 腹水
- 血便
- 血液凝固障害
- 肝性脳症 など
発症初期は症状がわかりにくいですが、食欲不振や多飲多尿、体重減少などが確認できます。
中度~重度になると、黄疸や腹水、血液凝固障害などの症状へ移行します。
銅関連性肝炎
銅関連性肝炎は、肝臓内の銅排泄が不十分となり肝障害を引き起こす病気です。
銅は体の健康を保つのに必要不可欠な成分であり、貧血予防や被毛の光沢がよくなるなどの効果が期待できます。
しかし、銅が過剰に蓄積されてしまうと肝臓に傷をつけてしまい、慢性肝炎や肝硬変などの疾病へ進行する恐れがあり注意が必要です。
また、銅関連性肝炎は特定の犬種で発症しやすいことから、遺伝的要因に起因する病気として知られています。
銅関連性肝炎を発症しやすいとされる犬種例は以下のとおりです。
- ベドリントンテリア
- ウエストハイランドホワイトテリア
- ドーベルマン
- ピンシャー
- コッカースパニエル など
次に、銅関連性肝炎の症状例をご紹介します。
- 食欲不振
- 多飲多尿
- 体重減少
- 元気がない
- 黄疸(目のまわりや歯茎が黄色くなる)
- 嘔吐
- 下痢
- 腹水
- 血便
- 血液凝固障害
- 肝性脳症 など
銅関連性肝炎の症状は慢性肝炎と類似しています。
素人目には区別できないため、獣医師による診察を受けるようにしましょう。
肝硬変
肝硬変とは、肝臓に長期間ダメージが蓄積され、組織が線維化し広がった状態をあらわすものです。そのため、特定の病気を指す呼称ではありません。
肝硬変の状態が進行すると、肝臓が正常な働きを失い肝不全に陥ります。
肝臓は20%以上の組織が正常であれば機能維持が可能だとされています。
そのため、肝臓の機能に支障が出る肝不全の状態は、組織の80%以上がダメージを受けている状態であり大変危険です。
また、一度肝臓が線維化してしまうと、症状の進行を遅らせることはできても元の健康な肝臓に戻すのは難しいとされています。
肝硬変の症状例は以下のとおりです。
- 食欲不振
- 多飲多尿
- 体重減少
- 元気がない
- 黄疸(目のまわりや歯茎が黄色くなる)
- 嘔吐
- 下痢
- 腹水
- 血便
- 血液凝固障害
- 肝性脳症
- 意識障害 など
初期の肝硬変の症状は、ほかの肝臓病と類似するものが多くあり見極めが困難です。
しかし、症状が進行すると肝臓の毒素分解機能が正常に働かず、それにともなった意識障害が発生します。
犬が肝臓を悪くする原因
犬が肝臓を悪くする主な原因は以下の4つです。
- 栄養が偏った食事を続けている
- 肥満
- 感染性
- 毒素
栄養が偏った食事を続けている
栄養が偏った食事は、肝臓に負担をかける要因となるため避ける必要があります。
肥満につながる恐れがある高カロリーな食品を減らし、高たんぱくのフードに変更するなどの工夫が大切です。
また、野菜や果物から摂取できるビタミン類は、抗酸化作用により肝臓病の改善に効果的だとされています。
肥満
高カロリーの食事ばかりあたえてしまうと肥満の原因となります。
「肥満は万病のもと」といいますが、それは人間だけでなく犬も同じです。
肝臓病のみならず、糖尿病や心疾患を誘発する要因にもなるため、運動や食事コントロールによる肥満防止は健康維持に大切な要素です。
感染性
ウイルスや寄生虫、細菌などが原因で肝臓疾患につながる恐れがあります。
しかし、ワクチンを接種することで未然に防げる場合もあります。
例として、急性肝炎の原因となるアデノウイルス1型による肝炎は、ワクチン接種によって予防できます。
ワクチンにはさまざまな種類があるため、獣医師と相談したうえで接種するワクチンやタイミングを検討しましょう。
毒素
肝臓に毒素が過剰に蓄積すると、急性肝炎などの肝疾患を引き起こします。
毒素は化学物質や薬物だけでなく、銅や鉄などの健康維持に必要な成分も含まれます。
そのため、食事やサプリメントによる過剰な成分摂取が行われないよう、飼い主さんがコントロールしなければなりません。
犬の肝臓病を診断する方法
犬の肝臓病は血液検査で診断可能です。
診断の指標となる項目は、GPT(ALT)、GOT(AST)、ALP、GGTなどがあげられ、これらの数値が上昇していると肝疾患の可能性が出てきます。
しかし、指標となる数値類は一時的に上昇する場合もあるため、犬の状態にあわせて複数回の血液検査が必要となるケースも一般的です。
血液検査の結果を踏まえ、さらにエコーなどを使った入念な検査を実施し、最終的な病気の診断をします。
犬の肝臓病の治療法
犬の肝臓病を治療する代表的な方法を2つ紹介します。
投薬治療
病気の種類によって使用される薬はさまざまです。
例えば、銅関連性肝炎の場合だと、肝臓に蓄積された銅を排出させるため、銅キレート剤を投与します。
犬の状態や病気の進行度合いによって使用される薬は異なるため、獣医師の話をしっかりと聞いたうえで、愛犬に投与する薬を選択するとよいでしょう。
療法食
肝疾患を患っている犬は肝臓の機能が低下しているため、日々の食事にも注意が必要です。
例えば、たんぱく質は肝臓の再生に役立つ成分です。
しかし過剰に摂取すると、分解の過程で発生するアンモニアによって肝臓へ負担をかけます。
また、銅関連性肝炎を患っている犬の場合だと、銅の摂取制限は欠かせません。
肝臓が弱っているところに銅が蓄積されると、さらに肝機能を低下させます。
市販で販売されている療法食もありますが、愛犬に適した商品を飼い主が独自に選ぶのは難しいです。
そのため、市販品から選ぶ際は獣医師の助言を受けたうえで検討しましょう。
犬の肝臓病の予防法
犬の肝臓病を完全に予防するのは困難ですが、日々の積み重ねによって病気から愛犬を遠ざける工夫はできます。
栄養バランスのよい食事をとる
栄養バランスのよい食事をとることで、愛犬の肝臓への負担を軽減させることができます。
ドッグフードなどの総合栄養食だけでなく、間食としてあたえるオヤツの種類や量も飼い主がコントロールする必要があります。
また、人間用の加工食品やお菓子は塩分などが多く含まれているため、犬にあたえるのは避けましょう。
定期検診を受ける
定期検診を受けることで肝臓病のみならず、ほかの病気やケガの発見にもつながります。
定期検診の頻度は犬の年齢や持病によって異なりますが、気になる数値や症状がある場合には、半年に1回程度を目安にするとよいでしょう。
※上記はあくまでも目安のため、獣医師と相談して定期検診の頻度を決めましょう。
肝機能をサポートするサプリメントを摂取する
肝機能をサポートするビタミン類や亜鉛などの成分が含まれたサプリメントを摂取するのも、肝臓病予防に効果が期待できます。
しかし、犬によってはサプリメントが体に合わない場合があるため、体調不良などの異変がみられたら、サプリメントの中止を検討しましょう。
まとめ
犬の肝臓病は知らないうちにやってきます。
愛犬の健康を守るためにも、病気の種類や症状、食事コントロール、肥満予防など、飼い主としての健康管理を怠らないようにしましょう。






カテゴリーの人気記事